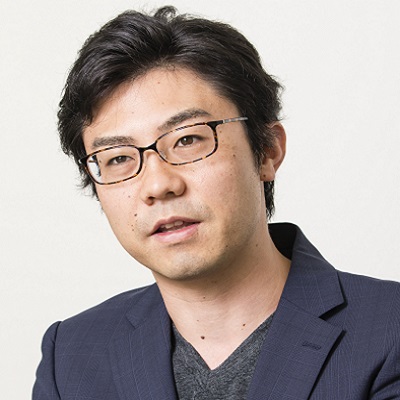業界で活躍する方々に、ファッションに関する様々な意見を聞くインタビュー
AECC (Asian European Consulting Company) 代表取締役社長齋藤 統

PROFILE
齋藤 統
1949年生まれ。73年、リヨン大学に留学。78年、日仏間の情報交換を主業務とするサブリンヌ社を設立。81年、ヨウジヨーロッパ社社長に就任。93年、AECCを設立。エグジル社、ジョセフ・ジャポン社、カサボ社社長を歴任後、2007年から3年間イッセイミヤケ・ヨーロッパ社社長を務める。08年フランス芸術文化勲章シュバリエ受章。現在は神戸芸術工科大学客員教授、和洋女子大学客員教授など。
海外に出る目的と目標、戦略、時間軸を設計し、その国に合ったビジネスを展開せよ
私は31歳の時、山本耀司さんとお会いして、ヨウジヨーロッパ社の社長に就任しています。その頃、私はすでにパリで会社を設立し、フランスのビジネスを多少知っていましたし、「僕が相手にしたいのは国内マーケットだけではない。世界中に発信していく手伝いをしてほしい」という耀司さんの言葉を粋に感じて快諾しました。
当時、黒を基調とした服をつくるデザイナーなどいませんから、最初は「引き裂かれた黒の“プアルック”に、誰が高いお金を出すのか」と酷評されました。しかし、耀司さんはまったく意に介さない。彼には「ヨーロッパのファッションに楔を打ち込んでやる」という気迫があった。それから4年後、彼は「マイスター」と呼ばれる存在に。お互い衝突も多々ありましたが、経営を全面的に任せてくれたことが大きかったと思います。
クリエイションと会社経営は両立が難しい。だからこそ、デザイナーとして成功するには、経営センスを持ったパートナーが必要です。デザイナーのイヴ・サン=ローランと社長のピエール・ベルジェがその好例でしょう。デザイナーが社長となって社会的責任を背負い、何か問題が起こるたびに判断を迫られる立場で奮闘するよりも、クリエイションに全力を尽くすほうがいい作品が生み出せるはず。デザイナーにとって一番ハッピーなのは、自分の好きなことが自由にできることだからです。
一方、経営パートナーに必要な資質は、マーケットはもちろん、服のつくり方も熟知していること。そして、パートナーの服が好きでありつつも、デザイナーという一人間に傾倒しすぎないこと。でないと、対等に意見を言うことができません。
フランスにいて感じるのは、日本の流儀をそのままフランスに持ち込んで、「うまくいかない」と悩んでいるデザイナーが多いこと。日本人と外国人では、好みも体形も異なりますし、ヨーロッパ人の体形に合わせていない服、腕も足も入らないような服をつくっても、当たり前ですが商売はできません。また、価格設定の考えも異なります。日本では、上代の60%を前提に“卸値”交渉をしますが、こちらでは最初に“卸値”で交渉するのが一般的。ヨーロッパの多くの国にはVAT(付加価値税)があり、売値の15%以上が税金です。手数料などを考慮すると、日本側は60%の卸値で販売しているつもりでも、こちらでは80%で仕入れる計算になる。現地では、そこに利益を乗せた価格で販売するので、売値が非常に高くなってしまう。だから、「60%の卸値なら要らない」となる。きちんとしたコスト計算をする癖がついていないのです。
才能があっていい服ができても、日本の流儀に固執すると、価格で負けてしまう。海外で勝負するには語学力も必要ですが、何より重要なのは、相手の国をよく知り、現地の生活や文化を受け入れ、そこに合ったビジネスを展開することです。
「パリに行きさえすれば道が拓ける」と思っているデザイナーから相談を受けることがありますが、そんな生半可な気持ちで、世界を相手に戦うことなど笑止千万。「なぜパリに行くのか」という目的と目標、戦略、そして、今スタートして何年後にどうなっていたいのかという時間軸。これらを明確に設計していなければ、成功などできません。
そういった意味で、今の日本に必要なのは、世界に通用する飛び抜けたスターをつくること。そのためには、国内の作品コンペティションの審査委員は全員外国人にするぐらいのことをしたほうがいい。外国人の感性に合う人材を育成することが、日本のファッション業界を活性化する一番の近道だと思うのです。